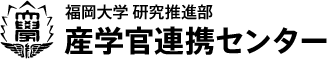ホーム 産学官共同研究機関研究所
産学官共同研究機関研究所
産学官共同研究機関研究所
福岡大学には、約1,400人の研究者(教育職員)がいます。日々、学生への教育活動や病院での医療業務に携わると共に、幅広い研究を行っています。産学官連携活動の推進を図り、研究成果の実用化の促進や社会貢献の実現を目的に、産学官共同研究機関研究所を設置しています。
※タイトルをクリックすると、各研究所の詳細が表示され、再度クリックで閉じます。2025年4月現在の情報です。
-
産学官共同研究機関研究所
福岡から診る大気環境研究所
福岡は日本最西端の巨大都市であり、国境を越えてアジア大陸から流入する大気汚染物質と日本の都市圏で排出される汚染物質がはじめて出会う大気化学的に興味深い場所に位置しています。これまで福岡大学では、福岡都市圏での大気汚染物質の動態と人間生活 (健康) への影響を明らかにするため、大学・研究機関・企業と連携し、日本最大級の大気環境物質の観測基盤を構築し、観測および研究を行ってきました。
本研究所では、その観測基盤を維持・発展させるとともに、膨大な過去および現在の大気汚染物質の観測データを複合的に解析し、大気中の物質の動態とその社会への影響の理解を進化させることを目指しています。また一般向けにわかりやすく大気環境について情報発信することで社会に貢献してまいります。- 関連リンク
- 福岡から診る大気環境研究所ウェブサイト
-
産学官共同研究機関研究所
材料技術研究所
「材料技術」は、工業製品の設計・生産のみならず、安心で安全な社会を支える基礎技術であり、幅広い研究対象を持っています。本研究所は、材料技術に関連する研究分野を対象に、「学際的・国際的」研究を行うプラットフォームを構築して新産業を創出することを目的としています。旧材料技術研究所では、材料強度と医工連携の研究を中心に組織の基盤固めを行いました。
本研究所では旧研究所の機能に、カーボンニュートラル実現に向け水素脆化研究を加え、時代のニーズに対応した先端研究を行います。カーボンニュートラルの実現には、文理融合した学際的なアプローチが必要ですので、将来的には、工学分野に研究対象を限定せず、文系も含む新しい学問領域を創出することを目指します。さらに、本学の研究者・学生と国内外の研究者や留学生が集結する国際的な研究拠点を構築して、その中で大学の実質的な国際化と国際感覚に優れたしなやかで力強い学生の育成に貢献したいと考えています。- 関連リンク
- 材料技術研究所ウェブサイト
-
産学官共同研究機関研究所
バンブーマテリアル研究所
竹は、成長が早く2ヶ月程度で成竹の長さに達するイネ科の植物です。昔から日本人の身近には竹が生育しており、この竹を生活用品、建築資材、食品などと様々な用途で活用してきました。福岡県(竹林面積第5位)を含む特に九州地方の放置竹林が大きな社会問題となっています。また、この問題は、地球温暖化にともない、関東以北の東北地域にまで拡大し、里山や山林にも浸入竹林による被害が生じています。この問題を解決するためには新しい竹の利活用をする技術が必要となります。
本研究所は、竹の持つ様々な特性を生かしつつ、SDGsやカーボンニュートラルに貢献できる新たな製品や技術開発することを目的に、行政機関、民間企業、民間団体と共同・連携しながら研究開発を行い、海外にもターゲットをあてながら社会貢献することを目指します。
-
産学官共同研究機関研究所
エネルギー物質利用技術研究所
エネルギー物質は、単位質量当りに高いエネルギーを有する物質の総称です。これらの物質は、ロケット推進薬、花火原料、エアバッグ用ガス発生剤などに使用されるなど工業的に有用な物質です。一方、ひとたび取り扱いを誤ると製造・貯蔵時に爆発事故が起こる危険性があり、また、通常の使用時(燃やした際)には有害ガスが発生するなどの問題があります。
このため、本研究所では、①エネルギー物質の安全化技術、②環境調和・低毒性エネルギー物質の開発、③エネルギー物質の新規用途開拓を研究の柱とし、エネルギー物質の利用技術の拡充を目指しています。
-
産学官共同研究機関研究所
半導体実装研究所
半導体の技術はITの発展に伴って大きく進歩し続けています。本研究所は、3次元に半導体を組み立て、高密度で高性能な電子部品を開発することを目指して、2011年4月に開設されました。場所は、福岡県糸島市に開設された「三次元半導体研究センター」内にあります。先端半導体を3次元構造に組み立てるために必要な要素技術を開発し、設計から試作、解析、試験までの一連の工程を行うことができます。また、設計手法や信頼性試験方法などに関する標準化を行うことも目標としています。
本学の研究員、大学院生だけでなく他大学、企業、福岡県産業・科学技術振興財団も参画した産学官が連携して研究開発を行う研究所です。- 関連リンク
- 半導体実装研究所ウェブサイト
-
産学官共同研究機関研究所
先端分子医学研究所
先端分子医学研究所(FCAM)は2008年度に「癌研究(診断・治療法開発)と基礎研究の推進」、「生命科学者の育成」を趣旨とした基盤研究機関として設立され、2022年度からは「癌の治療法開発」に特化した産学官共同研究機関として新たに始動しました。
これまでに副作用の少ない抗癌剤の開発を目指し、癌特異的な治療効果を示す化合物の探索を行ってきました。我々が樹立した細胞株と3次元培養の技術を融合することで、癌および正常組織を模した薬剤スクリーニングシステムを構築し、癌のみに効果を示す新しいタイプの化合物Pyra-Metho-Carnil (PMC)の同定に成功しました。PMCの標的としてオルガネラ関連タンパク質を特定しており、癌特異的な治療作用の詳細を解明することで新たな癌増殖機構の解明にも繋がるのではないかと期待しています。PMCは副作用が少ない上に多くの難治性癌に効果を示し、その派生物であるPMCDについては国際特許を出願しています。今後、より効果的な誘導体の開発ならびに特許出願・取得を目指すとともに、製薬会社・他大学等との産学官連携を推進することで、癌治療薬としてのPMCDの早い段階での実用化を目指していきたいと考えています。
-
産学官共同研究機関研究所
心不全先端医療開発研究所
心不全は、心臓病の中で第一位の死因で患者数が激増しています。最近は、心不全を如何に予防し(一次予防)、心不全患者の増悪を如何に早期に発見するか(二次予防)が重要となってきました。そこで、安価で簡易に非専門医でも心不全の早期発見できる先端医療機器の開発を目指しています。
先端機器開発の候補として、1)短期血圧変動測定による心不全発症および増悪の予測、2)経皮的胸腔内評価ディバイスによる胸腔内診断システムの構築による心不全発症および増悪の予測、3)心不全慢性期・在宅医療の現場でAIを活用したテーラーメイド医療の構築による心不全増悪の予測、これら3つを柱とした研究を進めています。
-
産学官共同研究機関研究所
身体活動研究所
身体活動研究所は、2008年度文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」として設置選定を受けて設立されました。本研究所は、身体活動の健康科学に関する研究を遂行し、科学的根拠に基づく予防から治療までの処方を構築することおよび健康科学の研究を推進するための中核として内外の研究者の共同利用に供することを目的として推進して参りました。2022年度より、産学官共同研究機関研究所として、国内外の関係機関との連携協力のもと、「身体活動の健康科学」の未解決課題に踏み込み、ミクロからマクロまでの包括的研究を展開し、生活習慣病の予防、介護予防、抗加齢に効果的な運動プログラムの開発と運動習慣形成を支援するシステムを構築することを目指します。
- 関連リンク
- 身体活動研究所(facebook)
-
産学官共同研究機関研究所
複合材料研究所
複合材料研究所では、医薬品、化粧品、食品、材料などの分野に応用されるナノメートル、マイクロメートルといった極めて小さな物質の構造を制御し、それらを組み合わせることで、従来法では実現できなかった機能をそれらの物質や素材に付与する研究を行っています。mRNA薬剤、難溶性薬剤に対して、超音波やリポソームを利用することでリン脂質や高分子と薬剤を複合化し、ナノサイズのドラッグデリバリーシステムを開発しました。化粧品や食品などに利用できる技術として、有害な有機溶媒を利用せずに高機能の製品を生産する技術、優れた電気(絶縁)特性を有する複合材料の開発などを行っています。
-
産学官共同研究機関研究所
循環型社会研究所
持続可能な形で資源を利用する「循環経済」への移行を目指すことが世界の潮流です。プラスチック資源循環に向けた取り組みも活発化している一方、廃棄物の分別収集については有害物を除外するための分別という側面もあります。粗大ごみの退蔵が災害廃棄物発生量の増加等につながる懸念もあるなど、新たな課題整理も求められています。特に高齢者等にとっては「難しい」知識が要求されること、粗大ごみに対する運搬の困難さ、地域コミュニティ自体の劣化等も懸念されています。多様化した住民ニーズに的確に応える資源回収システムの構築が不可欠です。
本研究所では、上記課題を鑑み、地域コミュニティに支持され、継続的に運営がなされるような資源回収拠点のあり方の検討を目的としています。
-
産学官共同研究機関研究所
資源循環・環境制御システム研究所
1997年に文部科学省の学術フロンティア推進事業および北九州市エコタウン事業の支援を受け廃棄物の無害化やリサイクルによる減量化、資源化の研究を行う研究所として北九州市エコタウン内の実証研究エリア内に設置されました。多くの共同研究プロジェクトを通じて、実用化技術の創出に努めてきました。現在はその研究成果を生かし、無害化技術や資源化技術の企業への技術移転とともに国内外の企業や自治体との新たな産学官連携研究を推進しています。
特に我が国随一ともいえる廃棄物大型実証施設やその研究成果をベースに自治体や企業を対象とした研究受託やコンサルティングサービスを推進し、総合的な環境研究所への展開を目指しています。- 関連リンク
- 資源循環・環境制御システム研究所ウェブサイト